- Home
- 第21回 日本語の中の中国語その9――虎は死して皮を残し、人は死して名を残す――|現代に生きる中国古典
第21回 日本語の中の中国語その9――虎は死して皮を残し、人は死して名を残す――|現代に生きる中国古典
- 2016/7/13
- 現代に生きる中国古典, 西川芳樹
- コメントを書く
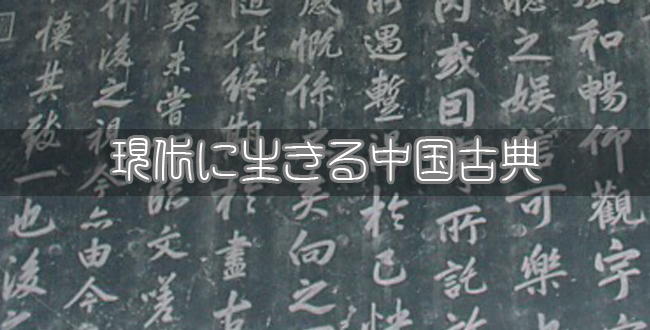
大河ドラマ『真田丸』が人気ですが、その主人公の真田幸村は、大坂夏の陣で不利な豊臣方に味方し、奮戦の末に壮絶な討ち死にをとげたことで知られています。大坂夏の陣では、真田幸村の他にも、後藤又兵衛や毛利勝永など多くの武将が豊臣家と運命を共にし、それぞれがその勇猛さと節義を讃えられています。そして、後の時代になると、彼らの活躍は講談や絵本(草双紙)、小説の題材として選ばれ、たくさんの物語が作られました。
中国でも、武勇と義を兼ね備えた武将は英雄としてあつかわれ、数多くの通俗的な物語が作られました。その代表はなんといっても『三国志演義』でおなじみの関羽でしょう。ですが、中国は長い歴史をもつ国、忠勇兼備の英雄も関羽一人ではありません。「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」の由来となった王彦章もその一人です。
王彦章は、五代十国時代に活躍した人物で、『新五代史』などの歴史書に伝があります。五代十国時代は、わずか五十三年の間に後梁、後唐、後晋、後漢、後周という五つの短命王朝が中原地域で興亡を繰り返し、多くの地方政権が現れた戦乱の時代でした。王彦章は、後梁に仕えた武将で、鉄槍を振るって大活躍をし、「王鉄槍」とあだ名されていました。ところが、後梁は、皇帝の失政などにより次第に勢力を失い、後唐に滅ぼされてしまいます。王彦章も抗戦しましたが、衆寡敵せず後唐に捕らえられてしまいました。後唐皇帝の莊宗は、自身も優れた武将だったので、王彦章の武勇を惜しみ、何度も人を遣って説得しました。王彦章は答えます「拙者は、陛下と十数年にわたり戦を繰り広げてまいりました。戦いに敗れて力つきた以上、死なずにおれましょうか。拙者は後梁の恩を受けております。死なねばこの恩に報いることはできません。朝は後梁に仕えておきながら、日暮れには後唐に仕えているようでは、天下に人々にあわせる顔がありません。」莊宗は、さらに説得を試みましたが、王彦章は「自分は生を惜しむものではない」と拒み、殺されました。
王彦章は、いつも人々に「豹は死して皮を留め、人は死して名を留む(豹死留皮,人死留名)」と言っていました。まさに、死によって忠義の名を後世に残したのです。
この言葉は、日本にもかなり早く伝わっていたようで、『日本国語大辞典』(小学館)を調べたところ、『古来風体抄』に「とらはしにてかはのこす。人はしにて名をとどむ」とあるそうです。『古来風体抄』は、1197年に初撰本が編まれ、1201年に再撰本が作られていますから、鎌倉時代初頭には、この言葉が日本に入ってきていたことになります。
ただ、日本では「豹」が「虎」へと変わっています。虎へと変わった理由は、はっきりしません。「虎死留皮」の用例を中国側の文献で探しましたが、明清代の資料にわずかにあるだけです。資料からは、中国語の影響かどうか分かりません。あるいは、『説文解字』に「豹、虎に似る」、『易経』の陸績注に「豹、虎の仲間で小型の者である」とあり、豹が虎に似た動物と理解されていたので、日本ではより有名な虎に変わったのかもしれません。変化の理由は分かりませんが、以降、日本では「虎は死して皮を留め(残し)、人は死して名を留む(残す)」という言い方が定着し、意味も死ぬことで後世に名を残すのではなく、「虎は死んだあともその皮が珍重され、偉業を残した人は死後もその名を語り継がれる」(『明鏡』)という意味で使われています。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

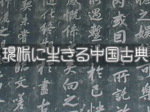

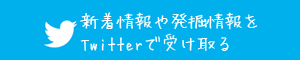

































 15 分チャイニーズ...
15 分チャイニーズ...
この記事へのコメントはありません。